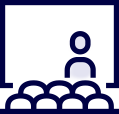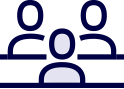必死に考え、形にしてきた唯一無二
株式会社アイスジャパン

松岡正昭氏
株式会社アイスジャパン 代表取締役
まつおか・まさあき。1954年、北海道夕張市生まれ。中学卒業後、
自動車整備の専門学校へ通い、整備工場やガソリンスタンドなど
で働く。1979年に室蘭で喫茶店を開き、店の常連客と1981年に
「アイスセンター室蘭」を設立、1984年から代表取締役に。
1993年に社名を「アイスジャパン」に変更した。
- 事業内容:
- 各種保冷剤・蓄熱剤の製造・販売、ドライアイスの販売、保冷バッグの販売、贈答品の販売
- 本社所在地:
- 北海道室蘭市
- 創業:
- 1981年
- 従業員数:
- 60名
「学歴がないのがコンプレックスだから、人一倍働いて、知恵を絞ってきました」
そうして社会の動きに合わせて業態を変えながら、常に自社製品やサービスに付加価値を求め続けてきた。そう笑いながら話すのは、アイスジャパンの社長である松岡正昭氏だ。同社は業務用保冷剤や高機能保冷剤の開発、製造、販売を主力事業とし、2023年5月期の年商は16億円。日本における保冷剤市場の3割を占め、国内トップシェアを誇る。
中学を卒業したあと、自動車整備の専門学校に通い、小さな整備工場やガソリンスタンドで働いていた松岡氏は、その当時流行っていたロックミュージシャン・矢沢永吉の『成りあがり』(KADOKAWA)という書籍に感銘を受けた。
「『近くにある自動販売機にベンツで買いに行く』のが矢沢の夢で、ミュージシャンとして成功した彼は、実際にベンツで自動販売機にタバコを買いに行っていたみたい。そんな成功をつかみ取るには、やっぱり自分で商売をやるしかない」
そう思った松岡社長は、室蘭で喫茶店「積み木」を始めた。そこで、のちの共同創業者と出会う。店の常連客で、建築資材の営業をしていたが、将来独立したいという思いが強い人だった。同人と話を重ねる中、飲食店で使う氷に商機を見出した松岡社長は、喫茶店を売却。1981年、アイスセンター室蘭を設立する。最初は、製氷業を行う会社だった。
「それまでは、トラックの荷台に載せた氷を、その場で切って売るのが一般的でしたが、私たちは違いました。今でこそコンビニなどで売られていますが、当時はまだ主流ではなかったロックアイスの形式にして、ビニール袋で包装して売ったのです。そっちのほうが衛生的だし、割る手間もかからないから、多少高くても売れると考えたわけです」

業務用から生活者向けまで、保冷剤や蓄熱剤を
さまざまな形で商品化し、展開している。
氷は1貫目が3.75㎏で、当時の売値は120円。スナックや居酒屋が毎日2貫目買ってくれて240円。高額商品ではないため、現金での回収がしやすい。さらに原料は水だから利益率が高く、毎日買ってもらえるリピート商品であるため、商売は好調だったという。
「スナックに飛び込み営業をして、夕方から夜にかけて100軒以上の飲食店へと配達するのは重労働でしたが、資金繰りなどで苦労したことはありませんでした」
ところが、創業から3年で、ともに事業を行っていた共同創業者が亡くなってしまう。松岡社長は1人、さらなる顧客獲得のために、さまざまな工夫を行った。
「当時、スナックや居酒屋では、氷をストックする場所がなかった。だから、買った氷は使わなくても次の日には解けてしまうため、毎日需要があったのです。そこで、3万8000円の48リットル縦型冷凍庫を200台購入して、氷を買ってくれる飲食店に、無料であげるキャンペーンを行いました。すると、室蘭エリアのスナック350軒を一気に制覇できたのです。苫小牧でも同じ手法で営業し、1年で100%のシェアを獲得しました」
その他にも、氷を買ったら店舗の損害保険に入れるサービスを考案するなど、さまざまな手段を駆使して“氷”を販売してきたのだ。差別化が難しい商品で、市場の面をとるには有効な戦略だといえる。しかし、その根底には、ただ商品を売るだけではない思いが存在していた。
「どうすれば飲食店の人に喜んでもらえるか、必死に考えた結果です」
保冷剤の製造を始め、売上の規模が変わる
時代が進むと、飲食店では製氷機を導入するのが一般的となった。製氷業をこのまま続けていくのは難しいと判断した同氏は、1986年、ドライアイスを仕入れて葬儀屋へ配達する仕事を始める。そして、1990年にドライアイスを買っていた会社で出会ったのが保冷剤だった。
「最初は何に使うものかもわからず、聞いてみると『ロシアからの毛ガニを本州に送るときなどに使う』という。それで興味がわき、つくり方を教えてほしいと頼んだわけです。するとドライアイスの仕入れ先担当者が展示会に連れていってくれて、そこで保冷剤の製造機械を購入しました。将来的に物流が拡大すれば、保冷剤の需要が増えると考えたことと、製造にかかる初期費用が安かったことで、挑戦を決めたのです」
さらに、製造機械や梱包資材を購入した会社の役員が、北海道内に15カ所あった支店や営業所すべてを紹介してくれた。営業に行くと、どの支店・営業所も保冷剤を買ってくれて、その売上は6000万円になる。
「氷を売って、1日10万円の売上ができればすごいといっていた商売の規模が、一気に大きくなりました」
商圏を全国に広げようと考えて、1993年に社名をアイスジャパンに変更。その後、東北や北陸などの需要も取り込み、2000年には商品輸送のスピードアップとコスト削減を図り、宮城県柴田町に製造拠点を設立した。今では、全国各地に6カ所の製造拠点を持ち、年間2億個の保冷剤の生産が可能だ。

北海道室蘭市に本社を構え(写真右)、全国5カ所にある倉庫(写真左)から、
国内外へと製品を供給する。
研究開発にコストをかけ、宇宙や医療分野へと広がる
一般的な保冷剤は、99%の水と1%のポリマーや防腐剤などでつくられている。ポリマーを混ぜることでゲル化し、袋が破れても中身が流れ出ない形状になるのだ。同じ機械と原材料を使えば、まったく同じ製品ができる。そこに特殊な技術は必要なく、やがては価格競争になるしかない。そのため、ピーク時は全国に150社あった保冷剤の会社が、現在では30社に減っている。その中でトップシェアを誇るアイスジャパンは、他と何が違うのか。
松岡社長は2005年、元NHKキャスターの野中ともよ氏が三洋電機の会長に就任したとき、経済誌に掲載された記事に衝撃を受ける。当時、経営難だった三洋電機が、3000億円もの費用を研究開発にかけているという内容だった。
「自分は、取ってきた注文をこなすことばかりで、研究開発費など考えたことがありませんでした。記事には、グローバルで戦う企業が開発費用をかけずに成長するはずがないとあり、革新的な技術で世にないものをつくらなければ、戦っていけないのだと感じ取ったのを覚えています」
ときを同じくして松岡社長は、山梨県富士吉田市にあるSTS研究所の佐藤正昭氏と出会う。佐藤氏は、もともと精密機器の研究開発をしていた人で、根っからの開発者。アイスジャパンとSTS研究所は、2008年から提携して研究開発を行うようになった。松岡社長は、「佐藤先生と知り合ったことで、製造業の本質が見えた」と語る。

1通の手紙から開発された、抗がん剤
治療中の患者向けの頭皮冷却「愛帽」。
佐藤氏との研究開発により、保冷剤に入れる製剤の配分を調整して、マイナス74 ℃からプラス100℃までの間で、指示された設定温度に保つことができる製品ができた。この技術は、のちの宇宙開発や再生医療などに応用されていくことになる。
2013年、宇宙航空開発機構(JAXA)からの依頼で、国際宇宙ステーション補給機「こうのとり4号機」に搭載された無電源輸送BOX用保冷剤と、国際宇宙ステーション実験棟「きぼう」に搭載された、無電源で氷点下74℃を3時間維持できる冷凍冷蔵庫用保冷剤を製造した。2016年に三重県で開催された伊勢志摩サミットで、iPS細胞を使った心筋シートが展示されたが、その保温にもアイスジャパンの技術が活かされている。
そんな中、2019年に乳がん患者の女性からもらった1通の手紙が、頭皮冷却用帽という新製品の開発につながった。
「手紙の内容は、抗がん剤の副作用である脱毛を防ぐため、頭皮を冷やす帽子型の商品はないか、という切実な問い合わせでした。抗がん剤治療時、頭皮を18℃程度に冷やすと、毛根へのダメージが少なくなり、脱毛が防げるというのです。急遽、佐藤先生に相談へ行き、3日間で試作品をつくって、手紙を送ってくれた方に届けました。その手紙は、今でも大切に持っています」
松岡社長は、その製品に「愛帽」と名付けて商品開発を進めた。100名のモニターによる臨床試験では、驚くほどの効果があったという。既存の高価な頭皮冷却装置と比べても同程度の効果が得られ、医療機器としての認可も取得。
最新モデルでは、手術後に手が上がりにくい患者からの声に応え、ダイヤルを回すだけで密着度を簡単に調整できるようにするなど、商品改良も怠らない。
願望を強くもつことで、それは100%実現する

同氏の経営方針は、すべてガラス張りにすること。社員なら誰でも見られる共有フォルダの中に、経営資料が入っているのだ。
「会社が持つ現金や利益、損失、借金がいくらあるのかなど、一目瞭然です。みんなが働いて稼いだ金を、私が管理しているだけですから、隠す必要もありません」
そんな経営者人生を振り返りながら、新しく事業に取り組もうと考えている経営者に必要なのは「強い願望」だと、松岡社長は指摘する。
「『こうなりたい、こうしたい』という強い思いがあれば、どんなことでも100%成し遂げられます。成功しない人は、思いが薄いだけ。中途半端は、絶対にダメです。強く願って、それを実現するため、徹底的に行動する。そして諦めなければ、道は必ず拓けるでしょう」
機関誌そだとう216号記事から転載