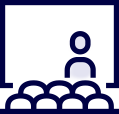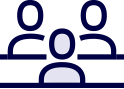世界を動かすMICE界での躍進
株式会社コンベンション リンケージ

平位博昭氏
株式会社コンベンション リンケージ 代表取締役
1954年神戸生まれ。1977年、同時通訳・国際会議運営会社に
入社。東京支社長などを経て1996年に株式会社コンベンション
リンケージを設立。1998年より株式会社イベント&コンベン
ションハウス(近畿日本ツーリストグループ)取締役兼務。
- 事業内容:
- 国際・国内会議、展示会、博覧会などの企画、運営、演出、広報、事務局代行。コンベンションセンター、文化ホール、複合施設などの運営・管理、マーケティングなど。
- 本社所在地:
- 東京都千代田区
- 代表:
- 平位博昭
- 創業:
- 1996年
- 従業員数:
- 1,230人(グループ含む)
G7やAPECなど、各国の首脳陣が一堂に会する国際会議をはじめ、ワールドカップなどの国際イベント、医学会、国際学会、展示会や企業イベントなど、さまざまなコンベンションやイベントのプロデュース事業を展開している、株式会社コンベンション リンケージ。
「会社の経営状況よりも、手がけている案件が成功裏に終わるかどうかを常に気にしている」と語る、根っからのプロデューサー気質である代表の平位博昭氏が1996年に創業し、今年で27年目を迎える。コロナ禍で多くのリアルイベントが中止に追い込まれた中でも、経営が傾くどころか、リアルとオンラインを駆使したHybrid Conventionを提案するなど、むしろ事業を拡大中だ。同社がこうして社会に求められている事実は、どんな時代においても、人々がリアルなコミュニケーションを重視していることの表れといえるだろう。
また、コンベンション リンケージはプロデュース事業以外にも、61のコンベンション施設や文化ホール、イベントホールなどを運営している。独立系の同業他社においては、日本最大規模を誇る業界のパイオニア的存在だ。そんな企業を生み育て上げた平位代表に、起業の背景や事業拡大に対する想い、そしてコロナ禍を経た今後の展望を聞いた。
戦後復興期の国際会議増加がMICEビジネスの始まり
同社が手がけるコンベンションビジネスは、「Meeting(会議)」「IncentiveTravel(報奨・研修旅行)」「Convention(政府主催会議・学術会議・業界会議)」「Exhibition / Event(展示会、見本市、イベント)」の頭文字をとり、「MICE(マイス)」と呼ばれる。コンベンションリンケージは、「E」に「Entertainment(娯楽)」や「Exposition(博覧会)」を加え、業容を広げてきた。
日本におけるMICEビジネスの起こりは、1964年の東京オリンピックや1970年の大阪万博のタイミングだ。同時通訳や翻訳を担う企業がいくつか生まれ、国際会議などの運営にも携わるように。やがてコンベンションやイベントそのもののプロデュースを請け負い始めて徐々に発展し、今日に至っている。
80年代、日本にコンベンションブームが到来。先駆けだった欧米に追いつけ追い越せと、幕張メッセや東京国際フォーラム、東京ビックサイトなど大型の会議場や展示場が次々に誕生した。しかし、期せずして91年にバブルが崩壊。日本が混乱に陥る中、コンベンションビジネスも他業界と同様に、再編へと舵を切った。平位代表は当時勤めていた同業の会社から独立し、コンベンション リンケージの立ち上げを決断する。わずか7人でのスタートだった。

1996年、創業当時の懐かしい写真(左)。7人という少人数でのスタートだったが、
今では多くの従業員を抱える企業へ成長(右)。その変化がよくわかる。
そもそも、同氏がこの業界に入ったのは、構造主義で有名なクロード・レヴィ=ストロースという社会人類学者がきっかけ。彼が国際シンポジウムのため来日すると聞き、大学生だった平位青年は彼に会いたい一心で、運営事務局へアルバイトとして入った。そのときに出会ったのが、コンベンションビジネス。すでに、大学卒業後に入社する会社が決まっていたのだが、「おもしろそうな業界だ」と、レヴィ=ストロースのシンポジウムで通訳を担当していた会社へ入社を決める。以来45年間、この道一筋で生きてきたという。

運営を手がける「奈良コンベンションセンター」(左)と「札幌
コンベンションセンター」(右)。同様の施設を61運営している。
常に高いクオリティで成果を出すノウハウがある
コンベンション リンケージの事業の柱は3つ。1つはコンベンションやMICEのプロデュース、もう1つは会場の運営、3つ目がそれに付随する同時通訳や翻訳、印刷物などのコミュニケーションツール制作だ。政府や国際組織が主催する大規模なものから、民間企業間の少人数会議まで、国内だけでも数えきれないほどのコンベンションが行われており、同社はそのうち年間2000件ものプロデュースや運営を担っている。
7人からスタートした会社は、グループ総勢1230人にまで拡大したが、平位代表は「会社を大きくしようと思ったことはない」と、意外な言葉を口にする。真意は「日本が1つの会社だと考えて仕事をする」という独自の思想に由来するものだ。
コンベンションビジネスはその特性上、属人的な仕事になりやすい。例えばAさんとBさんが同じ仕事を請け負っても、経験やセンスなどによって成果は大きく異なり、受注が偏るのが当たり前だ。コンベンション リンケージではその違いをなるべく少なくし、誰もがハイクオリティなアウトプットを行える仕組みをとっていると平位代表は語る。

専門性の高い医学会のプロデュースも手掛ける。(左)2022年に京都で開催
された「国際高血圧学会」。(右)2015年に京都で行なわれた「日本医学会総会」。
「専門性の高いプロフェッショナルを集めた、チームのエンジニアリング化です。通訳や音響、クリエイティブなど役割を細かく分け、各分野のプロフェッショナルを配置します。誰が依頼を受けてもチームの顔ぶれが同じならば、同レベルのものが生み出せるわけです。社内外を区別せずに、優秀な人をアサインする。『日本が1つの会社だと考える』とは、そういう意味です」
同社が成長したのは、そうしようと力を尽くしたからではなく、クオリティを意識して一つひとつの案件で成果を出し続け、リピートや紹介で仕事が増えた結果だ。
また、大規模な案件を手がけるには、それなりに人手がいる。大企業にしたいから採用を増やすのではなく、やりたい仕事に合わせて社員を増やしてきた背景があり、そこにも平位代表のプロデューサー感覚が反映されている。

コンベンション運営の功績に対して、さまざまな
団体から感謝状を受け取ることも多い。これは、
「国連防災会議」における国連からの感謝状。
長く経営を続けていても苦労はまったく感じない
「コンベンションビジネスのプロデューサーは、経営者と似ている」と、同氏は自身の経験から語る。どちらも成し遂げるべき目的があり、そのために人、物、情報をマネジメントしていく。大型国際会議ともなると、準備段階から当日のオペレーションに至るまでおよそ3000ものチェック項目をクリアして初めて運営が成功するが、会社運営も基本は同じ。法律の順守や資金調達など、多分野で1~2万ほどのチェック項目をクリアして、成り立っているのだ。
「それをいかにクリエイティブにやるのかという発想は、プロデュースも経営も変わらないでしょう。私自身、経営に関してそこまで頓着がなくても会社が成り立っているのは、プロデューサーの仕事を長くやってきたからかもしれません」
創業からこれまで「経営面での苦労はあまり感じませんでした。ホールで聴衆者が待っているのに講演者が現れないとか、国際会議で国旗の上下を間違えて掲示してしまったとか、仕事上の苦労や失敗はたくさん覚えていますけどね」と、笑顔で語るのも平位代表らしい。
1つだけ、コンベンションビジネスの大変さを語るとしたら、「キャッシュフロー上の問題。売上の入金が大幅に後になること」だとか。大型国際会議の場合、2~4年の準備期間を経て本番を迎え、事後処理の期間もあるので、運転資金が多額になる。大きな案件ほどやり繰りが難しい事業だ。創業当初は資金がなく、泣く泣くあきらめたこともあったという。
コロナ禍で機会が創出されたリアルなコミュニケーション
コロナ禍でデジタル化が進み、リアルな場を舞台にするビジネスは衰退するのではといわれる中、「それはないと確信しています」と平位代表は断言する。実際、リアルイベントの場はこれまで以上に増えており、依頼も殺到しているという。それは「オンラインによって人と人との接点が増えているから」だと同氏は分析する。これまで接点がなかった相手にオンラインで気軽にコンタクトをとれるようになり、「では今度会いましょう」と、リアルでの出会いが次々と想起されているのだ。
オンラインでのコミュニケーションが当たり前になればなるほど、逆にリアルのコミュニケーションの重要性が増してくると、平位氏は読んでいる。
「そもそも私たちの社会はコミュニケーションで成立しているリアルな社会で、映画の『マトリックス』のような世界になるには、100年以上はかかると思いますよ」

また、「人間はそうすぐには変わらないから」とも加える。実は2000年に、コンベンション リンケージはMICEにオンラインとリアルのハイブリッド運営を取り入れた「ネットコンベンション」の商標登録をとっていた。だからこそ、コロナ禍でも慌てることなくオンライン開催へと切り替えることができたのだが、20年前にはさほど重宝されなかったそうだ。
「新しい技術が生まれても、以前のやり方が楽だとか、新しいことを覚えたくないとか、覚えても意味がないという反発の傾向を強く感じました。何ごとも日の目を見るまでに20年はかかるのだと思います。だから、社員には20年後に花咲くものを今から準備しておいてと話しているんです。その頃、私は会社にはいないでしょうから」
そんなことを言いながらも、「もしもう一度やり直すのならば、ダイナミックな資本主義経済があるアメリカで起業したい」と、意欲にあふれた言葉が口をつく。
現役としてのバイタリティを持った経営者が率いる会社は強い。コロナ禍の逆風を追い風に変えて、さらに右肩上がりで歩んでいく姿が目に浮かぶ。
機関誌そだとう213号記事から転載